いよいよ試験が近くなってきました。
年長の受験生はコロナ禍で色々な情報が錯綜していますが、誰もわからないので仕方がないことです。
今回、学校説明会もしくは幼児教室で発信された情報を基に、試験傾向をまとめます。
下記は実際に発表された事実を基に挙げますが、可能性や予測にすぎないので、今後のコロナの展開を踏まえ、大手幼児教室に確認の上、適切な予測を行って頂ければと思います。
試験内容に影響を及ぼす可能性ありと明言している学校が多い
これまで多くの学校説明会に参加し、個別面談で質問もしていますが、試験内容を例年の内容から変更すると明言している学校が多いです。
具体的に何が?となると細かくお話している学校は少数になりますが、幼児教室では、5人集団のグループ活動を控えめにしている所が多く、出題可能性が低いと予測している教室も多いです。
私自身もグループ活動については、影響を受けると考えています。
この影響を受ける程度は、コロナ禍の度合いによるところですが、現時点で増加傾向であることを鑑みると、本年の試験では警戒モードは避けられず、何かしらの影響を受けることになるでしょう。
一方、試験日については、東京首都圏エリアにおいては大きな変動はありません。しかし、試験期間を長くする傾向があり、必然的に試験日も変わってきますので、同時に受けることができたり、できなかったりするケースが増えてくると思われます。
集団よりも個人の能力を問われる可能性大
各幼児教室で言われていることをまとめると、このような一言にまとめられます。
受験で集団感染になると、色々な意味で大問題です。
公になれば自宅待機となり、それ以後の受験は恐らくできなくなります。
受験生にも勝手に恨まれますが、学校側も併願する学校には当然に関与しないので、自己責任です。
ただ、このような事態は学校も望んでいないでしょうから、試験は集団でのかかわりは限定されたものになるでしょう。
細かく言うと制作物もどうか、という話になりますが、幼児教室発信ではここまで制約する予測は聞きません。
何かを作るとしたら、共同ではなく単独、運動するのも単独、口頭試問も単独、という流れになるでしょう。
複数人でモノを運ぶような課題の出題可能性は低いでしょうね。
野外活動経験よりも、コロナ禍での過ごし方
例年であれば、この時期、お子様に如何に多様な経験をさせられるか、という点がキーになります。
実体験を通じて、面接、口頭試問、絵画などに厚みを持たせることができるからです。
しかしながら、今年はこの経験の多くはプラスになりにくいです。
場所によっては自粛しない家庭と見られてマイナス評価になるでしょう。
当ブログでも過去に触れましたが、多くの幼児教室で重視するように指導しているのが、コロナ下での家庭での過ごし方。
これは「普通の生活の中で何を大事にしたか」という生活習慣や道徳面がテーマになるでしょう。
多用な経験であれば、尖った経験とそこで得たものをお子様が上手く話せればプラスに広がるテーマになりますが、
自粛環境下で自宅で何をしていたか、となるとややディフェンシブなテーマとなります。
言ってはいけないキーワードがいくつかあり、それを踏まないように話せれば及第点というところでしょうか。
これは準備していないと危険なテーマで、お子様が家でずっとテレビを見ていましたとか、勉強ばっかりしていましたとか、などどちらもダメでしょう。自由にお子様に話させると危ういテーマになりますので、対策は必須でしょう。
最後は体調管理
前の記事でもお話した論点になりますが、今年は例年と異なり、例えコロナでなくても熱が出たらそれで終わりでしょう。
体長が悪い方も無理して受験に来ると思われ、回数を重ねるごとにリスクが高まっていきます。
よって、10月の体調管理は非常に重要となります。この点、下記記事にまとめています。
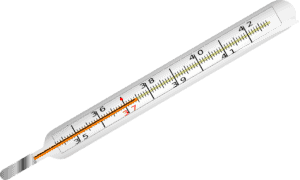



コメント